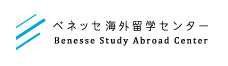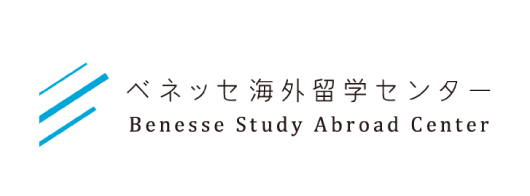高1・高2の夏、課外活動で何してた? ~アメリカ クレアモント・マッケナ大学 Ryu S.先輩~
海外大学を目指す際に重要なカギとなる「課外活動」。じっくり腰を据えて取り組みたいものの、高校生の日常は学校の課題やテスト、英語外部試験の対策などやることがいっぱい! まとまった時間が取りやすい夏休みは課外活動に取り組むチャンスです。アメリカのクレアモント・マッケナ大学に進学したRyu S.先輩に、出願準備が忙しくなる「前」の高1・2の夏休みに取り組んだ内容や出願での活かし方、アドバイスなど、課外活動についてたっぷりお聞きしました。
※ここでご紹介している内容は個人の体験です。実際に準備する際は、必ず最新の情報をご確認ください。

長期休みは課外活動に集中。オンラインの海外大プログラムや異文化交流など多彩に挑戦!
今回の「ラボ協力隊」

Ryu S.先輩
アメリカ クレアモント・マッケナ大学、国際関係学専攻 2年生(2025年秋〜)。
様々な学問を学べ、教授や友達と深い人間関係を築けることに魅力を感じ、アメリカのリベラルアーツ教育を志向。将来は教育制度の変革をしたいと考えている。
Q. 海外進学を意識して課外活動を始めたのはいつ? どんなきっかけ?
高1の冬、政治家との討議イベントに参加。以降の活動を広げる意欲に!
【海外進学を目指して本格的に課外活動を始めたのは… 高校1年生の12月頃】
私が海外大学に興味を持ち始めたのは、中学1年生の6月頃。ある米国大学の学長のお話を聞く機会があり、アメリカの大学の奨学金の多さに驚くとともに、親に負担をかけずに大学に行けるのではと思い、その頃から「海外の大学に進学してみたい」という思いが芽生えました。
とはいえ、中学生の頃は一度だけ学級委員を務めたことがあるくらいで、部活動や学校の委員会にはあまり積極的ではありませんでした。
高校に入ってからはすぐに、本格的に英語と学校の勉強に力を入れるようになったものの、海外大学を目指すにあたって何か課外活動を始めなければと思っていました。そんな中、先輩からの紹介をきっかけに、毎年議員会館で開催されている「高校生未来会議」*に参加しました。高校1年生の冬休みでした。
*全国高校生未来会議:全国の高校から一般公募・選抜された生徒たちが各党の政治家との交流を通じて政治に対する考えを深めることを目的とした討議イベント
学校外に友達があまりいなかったこともあり、様々な人と出会いたいという思いや、国会議員の先生がたと実際にお会いして交流してみたいという気持ちも大きかったです。
会議では、海外の大学を目指していたり、将来の夢について熱く語っていたり、LGBTQ+であることをSNSで発信しているような同世代の高校生たちと出会うことができました。これまでの自分の学校の友達とは異なるコミュニティの人たちだったので、視野が大きく広がりました。
当日、私の割り当てられたグループには素晴らしいメンバーが多く、グループ対抗の政策提言プレゼンテーションでは賞をいただくこともできました。この楽しかった経験が、後に様々な課外活動に積極的に応募しようという意欲につながったのだと思います。
また同時に、そこで出会った積極的なメンバーに触発され「もっと早くから課外活動に参加しておけばよかった」とも感じました。
私が1年生だった当時はコロナ禍で、授業はずっとオンライン、部活動もZoomで行われていました。対面での課外活動はほとんどなく、オンラインで参加できるものもありましたが、「まだやらなくてもいいかな」と思ってしまっていました。
しかし、課外活動はできるだけ早く参加することをおすすめします。アメリカの大学では高校が4年制のため、日本の中学3年生での活動も志願書に記入できる大学もあります。
学年が上がるにつれて英語試験の対策に追われるようになりますし、エッセイを書く上でも自分の体験や将来のビジョンが重要になります。だからこそ、早いうちから積極的に課外活動に取り組んでおくことが大切です。
Q. 高校時代に取り組んだ課外活動のうち、出願書類に記入した主なものは?
関心の高い社会課題に関する取り組みが中心。積極的な挑戦の結果、受賞も!
-
▼Ryu S.先輩の高校時代の主な課外活動
1.友人と制作した核兵器カードゲームのプレゼン
2.ヒップホップダンスのボランティア
3.国会議員と「ヤングケアラー」について意見交換会を企画・開催
- 1.友人と制作した核兵器カードゲームのプレゼン
高校の「平和探求プロジェクト」という放課後活動(希望者対象)の一環で、約10人のメンバーとともに、核兵器の脅威や被害、基礎知識について学べるカードゲームを制作しました。この活動では、ゲームをプレイする前後で意識調査を行い、結果をデータとしてまとめました。
この活動を通して「全国高校生フォーラム」にグループで参加し、「生徒投票賞」という上位4位に入賞しました。さらに、個人で「Change Maker Awards」に応募し、「全国大会銀賞」をいただきました。どちらの大会も英語でのプレゼンが必要だったため、英語とプレゼンの能力を磨く機会となりました。
元々プロジェクトのスタートから「全国高校生フォーラム」に参加することが決まっていたこともあり、ゲーム案の検討やデータ分析など、一つ一つ本格的に進めていきました。毎日のように新しいアイデアや改善案が出てきて、内容が形になっていく過程を楽しみながら活動を続けることができました。
その中で、友人の意見が自分と異なるときもありましたが、どう折り合いをつけて話し合いを進めるかを学ぶ機会になりました。また、グループでの発表においては、リーダーではなくプレゼンターとしてチームに貢献するという、自分なりの役割を見つけることができました。
そして、私の母校として「全国高校生フォーラム」で初めて受賞できたことは、大きな自信とモチベーションにもなりました。
その後、さらに自分の力を試したくなり、「Change Maker Awards」に挑戦することを決めました。日本語によるエッセイの審査、および英語による動画審査の地区予選・決勝を通過し、全国大会に進出。観客の前で7分間のプレゼンと質疑応答を全て英語で行いました。声の調子や身振り手振りなど、ネイティブの先生に見てもらいながら練習を重ねた成果もあって、全国2位に選ばれました。

Change Maker Awardsでのプレゼンの様子
- 2.ヒップホップダンスのボランティア
私が通っていたダンススタジオで、先生の助手として週に1回、約2時間の小・中学生向けのレッスンを4年間担当していました。それに加えて、ダンスの発表会やイベントの運営の手伝いや、スタジオのリノベーション作業にも協力しました。
一人っ子として育った私は、それまで年下の子どもたちと接する機会があまりなかったのですが、この経験を通して、どのように心を通わせるか、また振り付けをより覚えてもらいやすくするにはどう工夫すればよいかなどを考えるようになりました。こうした工夫や気づきを、大学出願用のエッセイにも書きました。
- 3.国会議員と「ヤングケアラー」について意見交換会を企画・開催
私はヤングケアラーの問題にも関心があり、この課題に取り組まれている文部科学大臣政務官に手紙を送りました。すると、議員からご返信をいただき、意見交換の機会を設けていただくことができました。そこで学校の友達で興味のある人を募り、5人で参加しました。
この意見交換会を通じて、ヤングケアラーは誰にでも起こりうる問題であり、若い子どもたちが一人で悩まなくてすむ社会をつくることが大切だと実感しました。
また、私たち自身が当事者になりうる存在であるからこそ、そうした状況に置かれたときに、どこに相談すればよいのか、どんな支援が受けられるのかを、もっと分かりやすく発信してほしいという要望をお伝えしました。
Q. 「高1・高2の夏休み」に取り組んだ課外活動は?
英語を活用するオンラインプログラムに参加。悔しさ、もどかしさも頑張る糧に!
- 【高1の夏】オンラインで英語を活用するサマーキャンプや講座などに参加
1年生の夏休みはコロナ禍だったため、私の高校が希望者向けに無料で提供してくれた、オンラインのサマーキャンプ「UC Irvine Leadership Program」に参加しました。海外大学の出願を見据えた課外活動というよりは、主に英語力の強化が参加動機でした。
全て英語で行われるプログラムに参加するのは初めてで、最初は教授に質問しようとしても、グループで発言しようとしても、言葉がまったく出てこず、とても悔しい思いをしました。
それでもプログラムの後半には、アメリカの地元高校生と直接話せる機会があり、せっかくのチャンスなのでどうにか質問をしようと、時間ギリギリまで英語で質問を考え、思い切って話すことができました。この経験が、英語のスピーキングを本気で練習しなければならないと強く思うきっかけになりました。
また、同じ夏には、「Coursera」という大学レベルの講義を無料または安価で受けられるオンラインプラットフォームで、自分の興味のあるテーマに関する講座を1つ受講しました。英語の勉強になるだけでなく、自分が将来大学で学びたい分野について、関心や意欲を実際の行動として示すことにもつながり、大学出願においてもアピール材料になったと思います。
さらに、英語のディスカッションクラブにもオンラインで参加しました。このクラブでは、毎週SDGsに関連するYouTubeやTEDの動画を事前に視聴し、Zoomで1時間ディスカッションを行うというものでした。
私はスピーキングに自信がなかったため、小学生のグループに割り当てられましたが、そのグループには海外在住の小学生が多く、とても活発に発言していました。負けたくないという気持ちから、毎回話す内容を事前にしっかり準備し、一生懸命取り組みました。
この経験を通じて、少しずつスピーキングにも自信が持てるようになりました。
- 【高2の夏】オンラインプログラムに参加し、多様なバックグランドの高校生たちと対話
「AFS Global You Adventurer」という、世界中の若者たちとともに異文化理解や自己探究を行うオンラインプログラムに参加しました。動画学習を活用してテーマ理解を深めながら、世界中の参加者たちと英語で交流するものです。
このプログラムは有料でしたが、私が参加した当時はエッセイを提出することで応募できる奨学金制度があり、ありがたいことに選考を通過して、奨学生として参加することができました。
2ヵ月にわたって、国籍やバックグラウンドの異なる同世代の高校生たちと対話を重ねる中で、ミーティングにおける発言の文化や思考の違いを肌で感じることができ、とても刺激的な体験となりました。
Q. 課外活動で大変だったり悩んだりしたことは? どう乗り越えればいい?
海外大受験はタスクがいっぱい!優先順位を決めて、課外活動は長期休みに集中。
私は、学校の成績、英語の資格試験の勉強、そして課外活動を全て同時に、完璧にこなすことは難しいと感じていました。そのため、自分の中で優先順位を決めて、「今はこれを深める期間」とテーマを絞って取り組むようにしていました。課外活動についても、数ヵ月前からネットで情報を集め、主に長期休みに集中して参加するようにしていました。
SNSでは、海外大学を目指している生徒が様々な活動を発信していて、私も最初は「同じことをしなければならない」と思い込んでいた時期がありました。でも本当に大切なのは、他人と同じ活動をすることではなく、自分が興味を持っていること(それが大学で学びたい分野であれ、関係ないものであれ)を深めていくことです。
課外活動は、将来のビジョンを描いたり、自分はどういう人なのかを理解したりする手助けになるものです。周囲に流されず、自分自身を表現できる活動を選んでください。課外活動に「正解」はありません。
また、大会や公募などでたとえ一度落選してしまっても、どうか諦めないでください。多くのプログラムには再応募のチャンスがあります。選考で何が評価されなかったのか、フィードバックをもらえることは少ないかもしれませんが、自分なりに反省して次に生かすことが大切です。
私自身、留学の選考や人気の課外活動では、「自分の経験や思いを、熱意を持って語れる人」「なぜそのプログラムが将来につながるのかを自分の言葉で説明できる人」が選ばれるのだと、受験を通して実感しました。
実際、私は「Stanford e-Japan」に2回落選しましたが、3回目の挑戦でようやく合格しました。1・2回目のエッセイは、今思えば酷い出来栄えだったと思います。
でも大学出願を経験し、何度もエッセイを書き直す中で、自分の考えを整理し、伝える力が身につきました。自分がどういう人で、どんなことを将来目指したいのかを明確に書くことも学びました。その成果が、「3度目の正直」につながったのだと思います。
Q. 課外活動の中でも、エッセイで取り上げるなど特に出願に活かしたことは?
内なる偏見を捨て、友人や先生と心を通わせられたことから得た気づきや学び。
全国高校生未来会議に参加した際、初めてLGBTQ+*の友達ができました。それまで自分では、偏見は持っていないと思っていましたが、いざ友達として接する中で、どう関わればいいのか正解がわからないと戸惑う自分に気づきました。
*LGBTQ+:性の多様性において数が少ない人である「性的マイノリティ」の総称
そんなとき、彼が「特別扱いするのではなく、一人の人間として、他の友達と同じように接してくれることが一番うれしい」と教えてくれました。LGBTQ+は彼の一つの個性であって、友人関係を左右するものではない。身構えず、ごく普通に接すれば良いのだと気づくことができました。
この経験と気づきがきっかけとなり、学校で仲の良かったネイティブの英語の先生が、私といろいろと話をする中で、ご自身がLGBTQ+であることを打ち明けてくれました。そのことはとても嬉しく、心に残る出来事となりました。卒業した今でも、その先生とは親しくさせていただいています。
課外活動に関するエッセイを書くときには、単に経験を並べるのではなく、たとえ小さな出来事であっても、自分の心がどう動いたのか、どんな気づきや学びがあったのかに焦点を当てて書くことが大切だと思います。そうすることで、自分らしい言葉で、自分自身をより深く伝えることができるはずです。
Q. 今だからわかる課外活動のポイントは? アドバイスもぜひ!
少しでも興味があればどんどん応募しよう!費用をかけずにできるものも活用して。
振り返ってみても、様々な課外活動に積極的に応募してきたことは本当に良かったと思います。私はネットで情報を毎日のようにチェックし、興味のある活動に何度も応募しましたが、落選も少なくありませんでした。そのため、海外大学を目指す多くの人が経験しているような活動には、なかなか参加できませんでした。
しかし、挑戦を続けた結果、当初はまったく想像していなかったような活動に関わることができ、自分ならではのユニークな経験を積むことができました。結果的に、それが他の人との差別化にもつながったと思います。
挑戦しなければ何も始まりません。だからこそ、少しでも興味があればどんどん応募してほしいです。
また、無料のオンラインプログラムに参加したり、自分で課外活動を立ち上げたりすることで、お金をかけずとも課外活動は十分にできます。そういった手段があることも、ぜひ多くの人に伝えたいです。
いかがでしたか?
多様な課外活動にどんどん挑戦し、自らの関心を行動に移す力を磨いていったRyu S.先輩。長期休みも活用しながら、英語を使ったオンラインプログラムや社会課題に関する実践的な活動に取り組んだことは、出願においても大きな財産となったようです。活動の羅列ではなく、経験から得た気づきや学びをどう言葉にするかが、志願書に深みを与える鍵になる― そんな先輩の言葉から、課外活動に向き合ううえでの大切なヒントが得られたのではないでしょうか。
LINE友だち追加で情報を逃さずゲット!
- 無料の海外進学イベントの情報
- 最新の記事更新のお知らせ
- 「簡単1分 留学おすすめ診断」 実施中

RECOMMEND
自分に合った進路に近づくための3つの講座をご紹介します