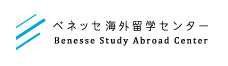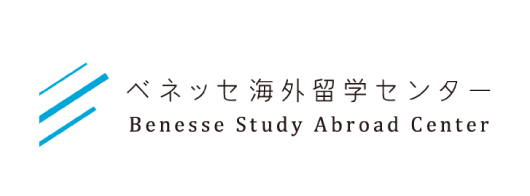アメリカの大学入試に必須のエッセイ、「書き始め」は何から?今日から回せるファーストステップ
アメリカの大学出願で大きな比重を占める「エッセイ」。成績やスコアでは伝わらない「あなたらしさ」を言語化して提出します。とはいえ、いきなり長いエッセイを書き切るのは難しいもの。そこで今日から始められる「書き始め」の実践ステップを詳しくご紹介します。

「エッセイ」とは? (基礎知識)
入試向けエッセイは、主にアメリカの大学入試で評価される出願書類の1つです。出願先が知りたい「人物像・価値観・学ぶ動機・将来の展望」を、具体的な経験を通じて筋道立てて文章で示します。また、日本国内でも、奨学金の応募書類としてエッセイが求められる場合があります。
アメリカの大学入試のエッセイ形式は大きく二つ。共通願書システム(Common Application)の共通エッセイ(上限650語)と、大学ごとに課されるサプリメンタルエッセイ(任意、設問形式で150〜500語が中心)です。
一方で、国内奨学金では、志望動機・学修計画・将来の貢献などとの整合性を、提示された文字数で簡潔に示すことが中心となります。
いずれの場合も、重視されるのはエピソードの「珍しさ」ではなく、その経験をどう生かし、何を学び、どう変化したか。つまり「経験→気づき→成長」が読み手に自然に伝わるかどうかです。大きな成果の羅列よりも、小さな気づきを掘り下げた一貫したストーリーが求められます。
〈エッセイの基本仕様:アメリカの大学入試〉
| 種類 | 語数 | 内容 | スケジュール目安 |
|---|---|---|---|
| 共通エッセイ | 〜650語 | 人柄、個性のコアを描く | 高2からエピソード洗い出し→高3で一本化 |
| サプリメンタルエッセイ | 150〜500語 | 大学独自の問いに答える | 語彙・切り口を設問に合わせる |
※詳細は、各大学や奨学金団体の公式サイトで最新情報をご確認ください。
今からやることは? (エッセイ執筆のファーストステップ)
最初から「長文を書き切ること」はしなくてOK。材料を増やす→短く試す→客観的な視点で修正 というサイクルを定期的に回すのがおすすめです。以下の5工程を数週間で一周させるところから始めましょう。
① 経験を洗い出す(棚卸し)
幼少期から現在までの、自分らしさに関わる出来事を時系列で書き出します。成功体験だけでなく、失敗・葛藤・挫折・違和感も必ず入れましょう。各出来事には「なぜ印象に残ったのか」「そこから何を学んだか」を一行で添えます。10〜20個を目標に、まずは粗くても量を優先し、紙や表に可視化します。
② 価値観の言語化をする
言語化した経験の中から、繰り返し出てくるテーマや行動パターンを拾い、3〜5つの「自分が大切にしてきた価値観」にまとめます。たとえば「少数意見を大切にする」「最後までやり抜く」など、行動が想像できる具体的な言葉にすることがポイントです。これが後のエッセイの軸になります。
③ 学びたいことと将来像を短く言う
「なぜその分野か」「社会のどんな課題に関わりたいか」を、分野×目的の形で100〜150字にまとめます。完璧さは不要です。仮の文章でも形にすることで、後のテーマ選定や大学別エッセイに流用できます。2案ほど用意し、使える語彙や表現を増やしましょう。
④ 「核」になるエピソードを選び、エッセイの骨組みを作る
あなたの価値観や目的に直結するエピソードを1つ選びます。「Before(状況)→Turning point(気づき)→After(変化)」の三段構成で3〜5行の骨子を作成。エピソードの珍しさではなく、その経験からの気づきと行動の変化を主役にします。読み手が成長の姿を想像できるように描くと、説得力が増します。
⑤短文試作→声に出す→修正
骨子をもとに150〜200語の短文に書き起こします。書き終えたら30秒で要旨を口頭で説明してみましょう。詰まった箇所や言いにくい部分は、その場で削ったりさらに具体化したりします。
そのあと第三者(先生・保護者・友人)に読んでもらい、「伝わった点/曖昧な点/印象に残った点」をもらい、即改稿。このサイクルを何度か繰り返すことで、自然と筆が進むようになります。
文章力や語彙の幅を広げるため、週のどこかで英語の多読も取り入れると効果的です。異なるジャンル(論説・小説・エッセイなど)に触れることで、表現のリズムや言葉選びが自然と身につきます。
月:棚卸し1件(20分)
火:英語多読(30分/ジャンルを変える)
水:価値観メモ100字(15分)
木:150〜200語試作(30分)
金:音読&自己添削(15分)
土:第三者フィードバック反映(10分)
日:微修正&翌週のネタ出し(20分)
いつから、どのぐらい対策する?
目安は高2の夏〜秋にスタート。最初の4週間で上記の①〜⑤を1周、その後8週間でテーマ別に2〜3周回すと、共通エッセイの候補が複数育ちます。高3の夏に大学リストが固まったとき、アプリケーションの設問に合わせた言い換え作業に着手できます。習慣化のポイントは「小さく、でも毎週」。素材が雪だるま式に増え、視点が磨かれていきます。
エッセイは「素材の質×編集力」の掛け算です。素材は日常の中で増やせます。短文試作と音読で小さく回し、第三者の視点で磨く。そのサイクルを早めにスタートさせておくことが、出願期の最大の武器になります。
Benesseでは、自己探求→価値観の言語化→テーマ設計→骨子作成→完成原稿まで、段階に合わせて伴走支援を提供しています。材料が少ない段階からのご相談も歓迎です。
※この記事でご紹介している内容は2025年8月15日現在の情報に基づいています。
LINE友だち追加で情報を逃さずゲット!
- 無料の海外進学イベントの情報
- 最新の記事更新のお知らせ
- 「簡単1分 留学おすすめ診断」 実施中

RECOMMEND
自分に合った進路に近づくための講座をご紹介します