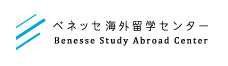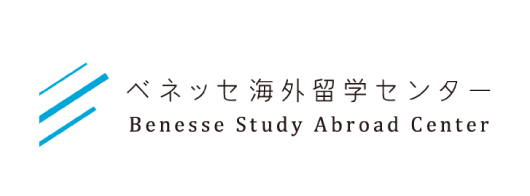SAT®のスコアクリアのための勉強、どうやって仕上げた? ~ウェルズリーカレッジ M.U.先輩~
アメリカの大学出願で広く求められる学力試験のひとつであるSAT®。総合的な学力を測るこのテストは、日本の高校生にとっては全て英語で出題されることもあり、形式や出題内容になじみにくく独特の難しさがあります。それでも、多くの受験生が出願に向けて高得点をめざし、限られた時間の中で工夫を重ねています。今回は、ウェルズリーカレッジに進学したM.U.先輩に、SAT®勉強法の実体験や、学校生活と試験対策を両立するためのポイントを詳しく伺いました。
※ここでご紹介している内容は個人の体験です。実際に準備する際は、必ず最新の情報をご確認ください。

対策講座+日常の工夫で英語力を底上げ。演習を重ねて本番力を磨きスコアアップ!
今回の「ラボ協力隊」
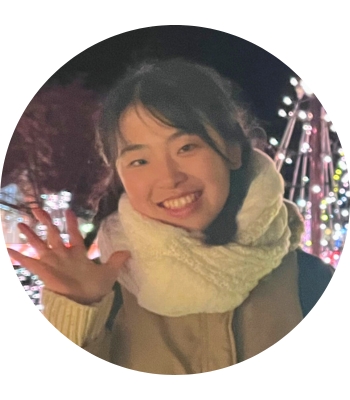
M.U.先輩
アメリカ ウェルズリーカレッジ 1年生(コンピュータサイエンス専攻予定)。
自分の限界への挑戦、学びたい領域の先進性にひかれて海外進学を志す。特にアメリカの文理横断の学びのスタイルが、自らの幅広く、分野をまたいだ興味関心の探究と相性が良いと感じ、リベラルアーツカレッジへの進学を決意した。
Q. SAT®受験を決めて、まず何から始めた?
大学の選択肢を増やすため受験を決意。SAT®対策講座を足がかりに勉強開始!
高校2年生の11月ごろに、ベネッセ Route G(当時はGlobal Learning Center*)のSAT®対策講座を受講し始め、勉強を始めました。
海外大学進学を考え始めた高校入学時は、コロナの影響で多くの大学がテスト・オプショナル(出願要件においてテストスコアの提出は任意とされる)へと移行しており、先輩方も受験していないかたが多かったため、SAT®の受験は真剣に考えていませんでした。
しかしながら、次第にテスト・オプショナルを撤回する大学が増えたため、大学の選択肢をできるだけ多く確保するためにも受験することを決めました。
*Global Learning Center:現在のRoute Gの前身
Q. 目標スコアに向けて、どんなスケジュールで進めた?
演習・実戦を重ねて2回目。文法問題への注力とケアレスミスの予防でスコアアップ!
-
【対策スタート】高2の11月
【受験】(1回目)高2の3月 →(2回目)高3の6月 →(3回目)高3の8月 →(4回目)高3の10月
高校2年生の11月に勉強を始め、直近の12月の試験申し込みはもう終了していたため、まず3月に力試しとして受験をしました。
3月は学校の試験や課外活動で忙しく、あまりSAT®の勉強に力を入れることができていなかったこともあり、スコアは1300点台で、芳しくありませんでした。しかし、実際に受験することにより、コンピュータを用いた試験の様子や時間配分などを今後の試験に向けて具体的にイメージできるようになりました。
その後、高校3年生の6月に再受験することを決め、読解問題よりも比較的点数をとりやすい文法問題に力を入れ勉強し、100点近く上げることができました。また、数学ではケアレスミスがないよう検算を日頃の練習から行うようにし、ミスのない計算を意識しました。
しかし、もう少し点数を上げたかったため、高校3年生の8月にも受験しました。夏休み中はTOEFL®を受験し、単語力が身についていたので、点数が上がることを期待しましたが、6月とあまり変化がありませんでした。
すでに3回受験し、満足のいく点数ではありませんでしたが、通常SAT®の受験は3回までが良いとよく言われるため、4回目の受験は検討していませんでした。しかし、Route Hの担当の先生と相談し、最後までチャレンジしてみようということで、Early Decisionの申し込み直前となる10月の試験も受けました。
4回目の受験では、当日の自分の不調と問題との相性があまり良くなかったことから、スコアアップは叶いませんでした。しかし、限られた時間の中で自分のベストを尽くせるよう最後まで頑張ることができたのは、後悔のない出願につながったと思うので、個人的には良かったです。
ただ、SAT®を出願ギリギリまで引き延ばすのはストレスですし、奨学金の準備や大学のエッセイとの勉強の両立も大変になります。出願直前の受験は、ドリームスコアまであと10〜30点ほど上げるための予備試験と考えておき、自分の出願大学に必要な最低限のスコアは高3の夏休み前までに取得しておくのが良いと思います。
Q. 日常生活や高校の勉強との両立、どう工夫した?
SAT®で学んだことの応用、スキマ時間の活用など日常の中で英語力アップを意識。
Reading and Writingを解くために、単語力を上げること、読解速度を上げることという、一夜漬けでは解決しない課題がありました。しかしながら、学校生活や課外活動で忙しく、SAT®の勉強に多くの時間を割くことができなかったため、日頃の生活に英語力向上を組み込むようにしました。
私は高校で、英語でIB(国際バカロレア)の授業を受けていたので、SAT®の過去問で出た単語やコロン(:)を用いたリストをエッセイに使ってみたり、英語のWebサイトで授業の予習復習を行ったりして、英語に触れる時間を増やしました。また、mikanという単語アプリを用いて、スキマ時間に単語を勉強していました。
Q. 教科ごとの勉強法や工夫は?
数学は関数電卓の使い方を練習、R&Wは過去問・公式の模試などを大量に演習。
【Math】
基本的に日本の中学〜高校1年生レベルの問題が多いことと、自分自身が数学は比較的得意な方だったため、あまり勉強には時間を割きませんでした。しかし、Mathの試験ではDesmosというオンラインの関数電卓を使う必要がある問題があるので、その電卓の使い方の練習はしました。
Desmosは、オンラインのWebサイトなので、GoogleやSafariで検索して日常的に使いながら練習できます。また、SAT®のBluebook(SAT®を運営するCollege Board公式の試験アプリケーション:受験者はこのアプリを自身のデバイスにダウンロードして試験を受ける必要がある)のWebサイトにある、本番形式の模擬テストでも使用することができます。
また、DesmosはMathの問題の全てで使うことができ、海外のYouTubeではDesmosの効果的な使い方を解説したものがたくさんあります。上手く使いこなせるようになると連立方程式や桁数の多い筆算を解く手間が省けるので、時間の短縮と答えの精度向上につながりました。
【Reading and Writing】
過去問やBluebookでの模擬テストはもちろん、無料の教材であるKhan Academyで、問題の解き方のコツや文法を勉強しました。SAT®は問題の数をこなして慣れていくことが大事だと思います。
そのため、BluebookのStudent Question Bankで、練習問題をたくさん解きました。Student Question Bankでは、問題の種類や難易度別に自分に適した練習問題の組み合わせを作ることができるので、苦手克服対策にもおすすめだと思います。
また、SAT®はTOEFL®と同様に4択の問題がほとんどですが、TOEFL®よりも選択肢に迷うものが多い印象があります。正しい答えを導こうとするよりも、消去法で確実に不正解である選択肢を外し、残った選択肢の細かなニュアンスの違いを理解して、正解に近い方を選ぶようにすると効率的に正答率を上げることができると思います。
Q. 実際に受験する中で気をつけたこと、工夫したことは?
時間配分に注意。タイマーで測りながら演習して1問70秒の感覚をインプット!
SAT®のReading and Writingは、長文読解が多いTOEFL®のReading問題と異なり、1パラグラフほどの短い文章問題がたくさん出ます。
27問を35分で解く必要があるため、1問にかけられる時間は70秒ほどです。そのため、時間配分がカギとなります。35分の試験時間を測りながら問題を解くのはもちろん、1問ごとにタイマーで時間を測りながら、70秒を感覚的に身につけられるようにしました。
同じ1問でも、SAT®の問題は、単語選択、詩の読解、グラフ読解、正誤判定、文法問題など種類が様々です。単語選択や文法問題は比較的文章が安易で短いため、かける時間を減らし、文章量が多い正誤判定問題により多くの時間を割けるようにしました。
基本的に、SAT®の試験の構成は毎回同じなので、どの部分に自分の得意な種類の問題があり、この時間までに何問解くべきかなどは、模擬演習などを通して把握しておくと良いと思います。
また、私のSAT®の受験は8時前に受付があり、とても朝が早かったです。そのため、試験1週間前からは特に早寝早起き、朝勉強を心がけ、早朝でも頭が働くような体内リズムを整えるようにしました。
Q. 振り返ってみて「これは良かった!」「もっとこうすれば良かった」と思うことは?
SAT®公式の練習問題で本番の傾向がつかめる!計画的な学習と早めの試験予約が◎。
【これは良かった!】
たくさん問題を解いた結果、類似した問題が本番に出たことです。特にBluebookの練習問題は、SAT®の運営団体が作成しているからこそ、問題の傾向が本番そっくりなため、解いていて損はないと思います。
また、SAT®の勉強計画はもちろん、試験の計画も行い、早めに希望の会場を予約するのが大事です。SAT®はTOEFL®に比べて、開催場所・回数が少なく、席数も限られているので、受験月を決めたらできるだけ早く予約すると良いと思います。
- 【もっとこうすれば良かった】
もっと計画的に勉強を進め、高校2年生までに目標スコアを取得できていればよかったと思います。高校3年生に上がると勉強がさらに忙しくなりますし、受験も本格的に始まり、スコアの重要度が上がるにも関わらず、思うように勉強の時間が取れなくなります。
何度でも受けられるからと、私は気が緩んだ勉強を特に前半はしていたため、結果的にSAT®と長期的に付き合うことになってしまいました。ストレスをできるだけ減らすためにも、短期集中で早めにスコアを取ることができていれば良かったです。
Q. これからSAT®を頑張る後輩へ、ぜひアドバイスをお願いします!
出願要件のスコアクリアは必須。でも点数に囚われすぎてストレスを抱えないように!
上記と矛盾するかもしれませんが、あまりスコアに囚われすぎないのも大事だと思います。トップ大学であればあるほど、SAT®の点数に差は出なくなります。実際に入学審査担当の方とお話しした際も、SAT®のスコアの良さだけが合格の決め手になるのではないとおっしゃっていました。
SAT®のスコアに囚われてストレスを抱えるよりも、課外活動に力を入れたり、エッセイの質を高めたりする方が、ひと際立った出願につながるのではないかと思います。
Q. Route G、Route Hなどベネッセのサポートで役立ったことは?
解くプロセスから理解できるので納得できる。迷った時の解答のコツも本番に活きた!
SAT®の講座では、答え合わせだけではなく、解き方のプロセスを先生と確認しながら進めることができました。そのため、問題集の解説だけでは理解できなかったところについて質問できただけではなく、答えが合っていても解き方を間違えているといった事態を防ぐことができました。
また、多くの問題を見てきたRoute Gの先生だからこそわかる、選択肢を迷った時の解答のコツは本番の試験でもとても参考になりました。
いかがでしたか?
SAT®対策において、過去問・公式の模試演習や日常的な英語力アップの工夫を積み重ねることが、本番での力につながったと話してくれたM.U.先輩。何から始めればよいかわからない人は、まず対策講座を足がかりに、解答のテクニックやコツを学ぶのもおすすめです。出願直前に慌てないためにも、早めに準備を始め、自分に合った方法で少しずつ力をつけていきたいですね。
SAT®対策に悩んでいる方へ
BenesseのRoute Gでは、海外・国内のグローバル系進路を目指す中高生に向けて、英語力の養成を中心にサポート。中高の英文法の速習から、TOEFL®などの資格試験対策、SAT®対策まで、進学に必要な力を段階的に育てます。少人数制のオンライン授業で、専門スタッフがあなたの挑戦をしっかり支えます。
INFORMATION
自分に合った進路に近づくための講座をご紹介します
LINE友だち追加で情報を逃さずゲット!
- 無料の海外進学イベントの情報
- 最新の記事更新のお知らせ
- 「簡単1分 留学おすすめ診断」 実施中